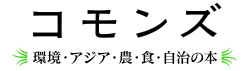新井綾香
四六判/184ページ/本体1700円+税
2010年6月/ISBN 978-4861870729
貧困は外部からの開発によってもたらされている!
農民とともに活動し、悩み、問題を解決していった20代の女性の真摯な4年間
プロローグ 豊かなラオス 「貧しい」ラオス
第1章 NGOに就職する
職業として国際協力NGOを選ぶ/障害者問題をとおしてプロジェクトの意味を考える
/JVCへの転職…
第2章 農村のリスク分散型の暮らし
農業技術者でない私が農業/農村開発に携わる/生存はできるけれど、生活はできない地域
/自給できなくても米を食べられる/「足を知る」精神…
第3章 失敗から学ぶチームづくり
エリートが多いNGOスタッフ/契約書をめぐる論争/苗の配布から苗づくりへ…
第4章 米不足への対応
薬か米か/「本当に貧しい世帯」が見えていない/悪循環の連鎖/村人が行う伝統的な田植え
/幼苗1本植えとの出会い/刺激としての中間評価を工夫/翻弄される村人…
第5章 開発の意味と支援者の責任
開発とは何だろう/NGOスタッフや行政職員の大切な役割/依存度を高めない支援
/支援者側の責任の自覚…
第6章 マクロレベルの問題とアドボカシー
保護林を伐採!?/知らされていなかった村人/NGOとしては黙認できない
/意志決定者へのアクセスが重要/地方に拠点があるからできるアドボカシー…
第7章 開発が貧困をもたらす!?
幼苗1本植えのリーダー的存在の村/セーフティーネットの役割を果たさない乾季作
/水田も森も奪われる/急激な変化と外部からもたらされる貧困/開発は貧困を削減するか?…
第8章 選択の危うさ
プロジェクトの終了/支援団体のポリシーか村人の優先事項か/選択のパラドックス…
第9章 外部者としてのNGO
草の根レベルと政策レベルの双方に取り組む/現場を変えるための政策提言
エピローグ 長い駐在を終えて
<解説>現場で鍛え上げた活動社の哲学:谷山博史
村人に寄り添って解決策を見いだす/現場で考えた豊かさと「貧しさ」
おわりに
新井 綾香(あらい あやか)
1977年 埼玉県川越市生まれ。
2001年 立教大学経済学部卒業。
2005~09年 日本国際ボランティアセンター(JVC)ラオス駐在員として、で農業・農村開発に従事。
共著『社会に尽くしますか、会社に尽くしますか凡人社、2005年』。
現在、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン職員(ベトナム、ミャンマー担当)。
書評オープン書評クローズ
本書は東南アジアの社会主義国ラオス農村部に、27歳から4年間NGO駐在員として農民とともに活動してきた女性の記録だ。一人の村人が雑談の席でつぶやいた「外から人が入ってくるようになって、自分たちは貧しいことを初めて知った」という言葉が忘れられなくなった著者は、「貧困とは何か」「何が開発なのか」を考え続ける。
草の根レベルと政策レベルの情報の橋渡し、政策が人びとにマイナスの影響を与えないかの監視、政策が正しく機能しているかの調査、政策を変えるための問題提起――の4点がNGOの重要な役割であり、使命だと綴る。ラオスはいま急速に開発が進む。悩みながらの活動記録は共感と示唆をもたらす。
『ガバナンス』(2010年7月号)
かつて、日本から第三世界へ「革命」の同志として旅立った若者たちがいた。多くの若者が、紛争地域にボランティアとして向かった時代もある。1977年生まれの著者は、職業として国際支援NGO(非政府組織)に入った。時代もやり方も変わったが、具体的に人々の役に立ちたいとの思いは同じだ。20代女性がラオスで3年半、農民と共に悩み、行動した日々をまとめている。
文体はやや報告書チックで硬め。その硬さにこそ、外部から農村に入り、当事者を尊重し、しかもある種の介入をする難しさと、それをやり遂げた誠実さが表れている。読みようによっては教科書的だが、読後感は、不思議なほどさわやか。本気で国際協力の現場を志向する人にとって、またとない本だろう。
『毎日新聞』(2010年9月26日)
『ガバナンス』(10年7月号、No.111)、『ふぇみん』(10年7月5日号、No.2928)、『国際開発ジャーナル』(10年8月号)、『毎日新聞』(10年9月26日)などで紹介されました。